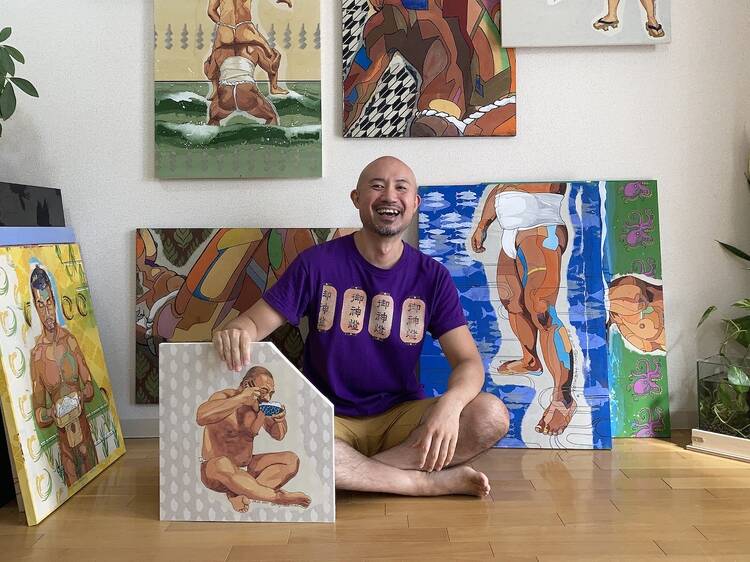レズビアン当事者の視点からライターとしてジェンダーやLGBTQ+に関する発信をする傍ら、新宿二丁目を中心に行われるクィアイベントでダンサーとして活動。
自身の連載には、タイムアウト東京「SEX:私の場合」、manmam「二丁目の性態図鑑」、IRIS「トランスジェンダーとして生きてきた軌跡」があり、新宿二丁目やクィアコミュニティーにいる人たちを取材している。
また、レズビアンをはじめとしたセクマイ女性に向けた共感型SNS「PIAMY」の広報に携わり、レズビアンコミュニティーに向けた活動を行っている。
https://www.instagram.com/honoka_yamasaki/